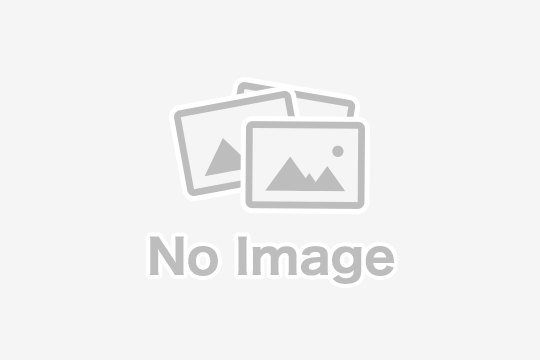白点病とは
白点病とは、ウオノカイセンチュウ(通称:白点虫、学名:イクチオフチリウス)が金魚の身体に寄生することで発症する病気です。魚体に1mm以下の白い点が無数に現れ、特にヒレや体表にポツポツとした症状が見られるようになります。
白点虫は「繊毛虫」と呼ばれる原生動物の一種で、同じ仲間にはツリガネムシなどがいます。自然界の水中にもともと存在していますが、水槽には最初からいるわけではありません。新しく導入した金魚や水草、底砂などに付着して持ち込まれるケースが多いです。
白点病の卵・幼虫・成虫のサイクル
白点虫のライフサイクルは、水槽環境において特に注意すべきポイントです。自然界では天敵や環境要因によってある程度制御されますが、水槽のような閉鎖環境では増殖を止めることが難しくなります。
まず、遊走子と呼ばれる白点虫の幼生が金魚の体表に取り付きます。そこで粘膜の中に潜り込み、魚から栄養を吸収して成長していきます。成熟すると魚の体表から離れ、水槽内の底や壁に付着して「シスト」と呼ばれる硬い殻を形成します。
このシストの中で分裂を繰り返し、1つのシストから最大3000個近い胞子が作られます。とはいえ、実際に水中に放たれ、遊走子として泳ぎ出る数は300以下とされており、さらにその中で生存できる個体はごくわずかです。
生き残った遊走子が再び魚に寄生すれば、同じサイクルを繰り返します。寄生→成長→離脱→シスト形成→胞子放出→再寄生という循環が、白点病の厄介さを生み出しているのです。
この一連のサイクルは、水温によりスピードが大きく左右されます。平均的には5〜10日で1サイクルを終えます。
白点病のサイクル
- 遊走子(幼生)が魚の体表に寄生
- 水中を泳いで魚の粘膜に取り付き、寄生を開始
- 寄生したまま栄養を吸収して成長(成虫へ)
- 魚の粘膜から栄養を取りながら体内で成熟
- 成虫が魚の体から離脱
- 成熟しきると魚体から離れ、次の段階へ
- 水槽内の底や壁などに付着してシスト(被嚢)を形成
- 殻に覆われたカプセル状の構造に変化
- シストの中で細胞分裂を繰り返し、最大3000個近い胞子を生成
- 分裂によって数百〜数千の子虫(胞子)を作る
- シストが破れて胞子(=遊走子)が水中に放出される
- シストから出た遊走子は次の寄生先を探す
- 再び遊走子が魚に寄生できればサイクルが継続
- 寄生に成功した個体だけが生き残り、再び1へ
※1サイクルにかかる期間は水温によって異なり、5~10日ほどが一般的です。
※寄生に成功できなかった遊走子は短時間で死滅します。
厄介なポイント
白点病が一度発生すると、水槽内に目に見えない遊走子が広がっている可能性が非常に高くなります。たとえ白点が治まったように見えても、シストや胞子がどこかに残っており、再発するケースも少なくありません。
特に注意が必要なのは、最初に白点虫がどこから入ってきたのかを特定することが難しい点です。新しい個体や水草が原因であることも多いですが、はっきりとは分かりません。だからこそ、新たな魚や植物を導入する際は、事前にトリートメントを行うことが重要です。
温度による変化
白点虫は広い温度帯で活動が可能で、2℃〜25℃の間では非常に活発に増殖します。一般的に、白点病の治療では「28℃以上に加温する」という方法が取られることがありますが、この温度では増殖スピードが落ちるものの完全に死滅するわけではありません。
実際には、温度が高くなることで白点虫が魚体から離れやすくなるだけで、シストとして耐えながら環境が整うのを待つことがあるため、温度管理だけで完治させるのは難しいのが現実です。
加温治療は有効な手段のひとつではありますが、それ単独では不十分であり、塩浴や薬剤の併用など総合的な対策が必要です。
発生原因
白点虫は自然界や水槽内の水中に存在していることがありますが、存在するからといってすぐに白点病を発症するわけではありません。実際、同じ水槽内で飼育している金魚のうち、発症する個体とそうでない個体が出ることがあります。
この違いは、主に金魚の体力や免疫力によって左右されます。特に、水質の悪化や急激な水温の変化といったストレスが加わると、金魚の体力が落ちて白点虫に寄生されやすくなります。つまり、白点病の直接的な原因は白点虫の存在ですが、発症の引き金になるのは「ストレスによる体力低下」です。
例えば、以下のような環境要因が金魚にとって大きなストレスとなります。
- 水質の悪化(アンモニアや亜硝酸の蓄積など)
- 急な水温の変動(特に水替え時に要注意)
- 過密飼育による酸素不足や縄張り争い
- 外部からの音や振動などの物理的刺激
- 水槽内でのいじめや争い
- 長時間の輸送による疲労
こうしたストレスを日常的に受けている金魚は、免疫が落ちて白点虫に狙われやすくなります。特に水替え直後や新しい個体を導入した直後は注意が必要です。
二次感染の原因にも
白点虫が金魚の体表に寄生すると、金魚は強いかゆみを感じるようになります。そのため、水槽の壁や底砂に身体をこすりつける「フラッシング」と呼ばれる行動が見られることがあります。この行動により体表が傷つき、その小さな傷口から細菌が侵入することで、穴あき病や細菌性皮膚炎などの二次感染を引き起こすケースもあります。
こうなると白点病に加え、複数の症状を同時に治療しなければならず、金魚の体力的な負担も増してしまいます。白点病は比較的治療しやすい病気ではありますが、放置して二次感染を招くと回復が難しくなるため、初期対応が非常に重要です。
白点虫の寄生を防ぐには、単に薬で対応するだけでなく、ストレス要因をできるだけ取り除くことが最大の予防策となります。
有効な薬
白点病の治療には、色素剤の使用が非常に有効です。補助的に0.5%の塩浴を併用すると回復を早めることもありますが、絶対条件ではありません。
白点虫は、体表に色素が付着すると死滅するという特徴を持つため、「色素剤」と呼ばれる薬が駆除に用いられます。中でも効果的とされているのが、
- メチレンブルー
- マラカイトグリーン
の2種類です。
この2つはどちらも白点虫に対して高い効果がありますが、性質が少し異なります。メチレンブルーは金魚にとって毒性が非常に低く、安全性の高い薬です。
ただし、マラカイトグリーンと比べるとやや効果が穏やかで、治療に時間がかかることがあります。一方、マラカイトグリーンはメチレンブルーよりも10倍近い毒性があると言われていますが、そのぶん白点病への治療効果は非常に高く、速やかな回復が期待できます。
とはいえ、この「毒性」はあくまで比較上の話であり、実際には金魚に対するダメージは極めて小さく、安全に使用できる薬剤です。
むしろ、細菌性の疾患に使われるようなオキソリン酸系やフラン系(例:観パラD、グリーンFゴールド顆粒)の薬と比べれば、マラカイトグリーンの方がずっとやさしいとされています。さらにやさしいのがメチレンブルーで、魚が弱っている場合でも安心して使えます。
したがって、金魚が元気な状態で白点病を発症しているならマラカイトグリーンを、弱っている場合にはメチレンブルーでじっくり治療するのが適切な判断といえるでしょう。
塩浴の方法については、別ページで詳しく解説しているので、そちらも参考にしてください。
鷹の爪(唐辛子)は有効か?
白点病の民間療法として、「鷹の爪(唐辛子)」が効果的だという情報を見かけることがあります。しかし、これは根拠のない話です。
そもそも白点病の原因となるウオノカイセンチュウ(イクチオフチリウス)は「菌」ではなく「原生動物」に分類されるため、殺菌作用を持つ唐辛子成分(カプサイシン)では駆除できません。
唐辛子には多少の抗菌効果があるため、「傷口に侵入する菌の活動を抑えるのでは?」と考える人もいますが、それも限定的で、殺菌を目的とするならば、唐辛子よりも水換えや薬剤の使用のほうがはるかに有効です。
また、観パラDやグリーンFゴールド顆粒といった殺菌系の薬も、白点虫そのものには効果が薄いことがわかっています。これらは細菌に対して強力な効果を発揮しますが、白点病の原因である原生動物には本来の目的として使われるものではありません。
どうしても色素剤に加えて殺菌効果も期待したい場合には、「グリーンFゴールドリキッド」という製品が選択肢に入ります。これはメチレンブルーに「アクリノール」という殺菌成分を加えた薬剤で、色素効果と軽い殺菌効果を同時に得られる便利な製品です。
白点病の治療では、原因と薬剤の性質をしっかりと理解して、適切な選択をすることが重要です。民間療法に頼る前に、効果が実証されている方法を選ぶことが、金魚を確実に回復へ導く第一歩になります。
治療方法
白点病の治療にはいくつかの方法がありますが、中でも確実性が高いのは薬を使った治療です。たしかに28℃以上に加温することで白点虫の活動を鈍らせることは可能ですが、これはあくまで「休眠状態に追い込む」という消極的な手段に過ぎません。完治を目的とするならば、加温だけに頼るのではなく、薬浴や塩浴との併用が重要です。
メチレンブルーやマラカイトグリーンといった色素剤は、白点虫の遊走子に対して非常に有効です。塩浴だけでも自然治癒するケースはありますが、再発のリスクを抑えるためにも、薬を併用した方が安心です。塩浴は0.5%濃度が基本ですが、病状や魚の体力に応じて調整してください。
水換えのタイミングは目安として2日に1回程度とされていますが、水槽の汚れ具合や薬の効果を見ながら判断するのが実際的です。
- メチレンブルーまたはマラカイトグリーンを使用した薬浴が基本
→ 色素剤は遊走子(泳ぐ幼虫)に効果がある - 0.5%の塩浴を併用すると効果的
→ 魚の体力回復と薬効の補助に役立つ - 加温(28℃以上)は補助的手段
→ 白点虫の活動を鈍らせるが、完全に死滅させる効果はない - 水換えは2~3日に1回を目安に実施
→ 水の汚れや薬の効果に応じて調整 - 治療期間は5~10日間が目安
→ 白点虫のライフサイクルに合わせる必要がある - 治療中はエサを与えず断食させるのが望ましい
→ 水質悪化を防ぎ、薬の効果を最大化するため - 水換え時には以下に注意:
- 水温を前と合わせる
- 塩分濃度を0.5%に保つ
- 薬の濃度も調整する - 白点が消えたら薬浴・塩浴を終了し、通常の水に戻して2~3日観察
→ 再発がなければ本水槽に戻してOK - 治療中は強い光を避ける
→ 色素剤は光で分解されるため、直射日光やLED照明を遮る - 薬の色が薄くなったら適量を追加補充する
薬が効くのは遊走子のみ
白点病の治療に使われる色素剤は、どの段階の白点虫にも効くわけではありません。効果があるのは「遊走子」と呼ばれる水中を泳いでいる段階のみです。
成虫はすでに金魚の粘膜の中に入り込んでおり、薬が直接届かないため無力です。また、成虫が体表から離れて作る「シスト(被嚢)」も薬剤が中に浸透しない構造になっており、こちらにも薬は効きません。
そのため、治療の際は遊走子が水中に現れるタイミングを狙って駆除する必要があります。つまり、見えている白点だけに対応しても不十分で、見えない段階で対処を続けることが完治につながります。
治療期間と管理
白点虫はシストから孵化し、寄生・成長・離脱して再びシストを形成するまで、水温にもよりますが約5~10日間のサイクルで動きます。このサイクルを考慮して、治療期間も最低5日、長ければ10日以上を見ておくのが安全です。
治療期間中は餌を控え、可能であれば断食させることで水の汚れを抑えましょう。水が濁ってきたら、全換水を行います。2~3日に1度の頻度での全換水が推奨されますが、状況に応じて柔軟に対応してください。
水を入れ替える際には以下の点に注意が必要です。
- 水温は必ず前と同じにすること
- 塩分濃度(0.5%)を維持すること
- 薬の濃度を正確に再調整すること
このように慎重な管理を続け、魚の身体から白点が完全になくなったら塩浴・薬浴を終了して構いません。その後は通常の水に戻し、2~3日ほど様子を見て再発がなければ本水槽に戻してOKです。
注意点
治療に使用するメチレンブルーやマラカイトグリーンといった色素剤には、ひとつ注意点があります。それは、光に弱いという性質です。強い光に当たると薬が分解され、効果が徐々に薄れていってしまいます。
室内の照明程度なら問題ありませんが、直射日光や水槽用LEDライトのように強い光源が近くにあると、薬の分解が急速に進む恐れがあります。そのため、治療中はできるだけ強い光を避け、暗めの環境を保つようにしましょう。
薬が分解されていくと、水の色が薄くなっていきます。その場合は、薬剤を適量追加して、常に有効な濃度を保ってください。薬が効いている間にできるだけ多くの遊走子を駆除することが、白点病の完全な治癒につながります。
白点病の治療例
ここからは白点病の金魚を実際に治療していく様子を動画と写真付きでお見せします。
今回の治療では
- ヒーターあり
- 1日に1回エサあり(パラクリア)
- 0.5%塩浴
- アグテン(マラカイトグリーン)
- 時期は4月
- 2匹
の条件で行います。





薬はメチレンブルーでもよかったのですが、アグテンの方が効果が高く早く治るのでアグテンを選択しました。ただ、効果が高いということはそれだけ金魚にも毒性があり、★にしてしまう可能性も高まります。
薬浴や治療に慣れていない方や、個体がまだ小さくても体力がない場合はメチレンブルーを使用して★にしてしまうリスクを減らしましょう。
また、ヒーターで加温することにより白点虫のサイクルを早めたいと思います。
1日目
目では見えない白点虫がこのようにたくさんついています。カメラで拡大するとよくわかりますね。
金魚が壁に身体をこすりつけている場合は、白点病の可能性があります。
0.5%の塩浴にプラスしてアグテンを投入しました。この日はパラクリアを与えました。
3日目

約10Lの中で塩浴を行っています。
2日目に水の約7割を交換しアグテンも添加しています。
繰り返しますが、アグテンはメチレンブルーよりも効き目が強いので、メチレンブルーで薬浴するときよりも早く白点がなくなっている感じがします。
薬だけではなく、ヒーターによって白点中のサイクルを早めているのもポイントです。


白点の数は1日目よりも大幅に減り、キャリコも更紗も肉眼では1点のみが確認できる程度です。
塩浴前は背びれを閉じてじっとして元気がありませんでしたが、今は背びれもピンと伸ばして元気です。
7日目
キャリコ琉金は治療の甲斐なく★になってしまいました。かなり気に入っていた体の模様だったので悲しいです。
一方の更紗琉金は無事に完治して、本水槽の方に戻しています。